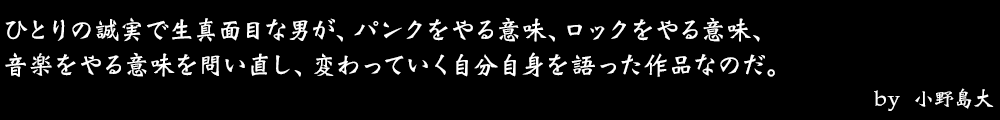作品レビュー:No.002 小野島 大
いわゆる客観的な視座によって作られたドキュメンタリーではない。終始一貫して(最後にもうひとり、意外な語り手が登場するが)横山健本人のひとり語りで綴られる、横山健の、音楽と人生。幼少のころの話も、ハイスタ結成のいきさつも、驚異的な成功を収めた90年代の栄光やその裏の苦悩や葛藤や挫折も、ソロになってからの着実な活動も、すべてが横山の主観のみで語られる。ようやくハイスタの幻影を振り切り、ソロ活動が軌道にのったまさにその時期に起こった3.11の衝撃。映像のトーンは一気に急転する。多くの人たちでそうであったように、横山の意識も音楽家としてのあり方も人生も、大きく変わる。そしてここで初めて、この映画が横山の主観のみで語られる意味のようなものが浮かび上がってくるのである。つまりこれはよくあるミュージシャンの成功譚や内幕ものや客観を装ったストーリーではなく、ひとりの誠実で生真面目な(・・・というには、いろいろふざけ過ぎな様子もふんだんに収められているが)男が、パンクをやる意味、ロックをやる意味、音楽をやる意味を問い直し、変わっていく自分自身を語った作品なのだ。
もちろん、ここでは語られない/語れないこともたくさんあるだろう。44歳の男の人生。きれいごとだけでは済まない事情も多々あったはずだ。たとえば3.11以前のぼくとのインタビューで、横山は「ハイスタをもう一回やるとしたら、理由はひとつしかない」と語っていた。その<理由>について彼は語ろうとしないし、もちろんここでも語られない。だがそんな事情など関係なく、震災の壊滅的被害を目の当たりにすることで、「やらなければいけない」という使命感のみで、ハイスタはまさかの再始動を果たし、AIR JAMまでも復活させてしまった。「自分の中で一番使える手札」としてのハイスタとAIR JAM。手段としてのハイスタ、道具としてのAIR JAM。だがそうすることで、KEN YOKOYAMA BANDでもPIZZA OF DEATHでも届かない領域に、確かに達したのだ。
「パンクが手を手をとってどうするんですかって感じですね(笑)。パンク・バンドのライブで目の前でね(中略)みんなで肩組んでマイムマイムして、それなんだよっていう。ずーっと思っていたんですよ」(2010年、『FOUR』発売時のインタビューより)
と、群れることを嫌い、パンクの孤高さを語っていた横山が、東日本大震災を機に変わる。繋がることの大切さ、助け合うことの価値のようなものを信じ、歌うようになった。背中に日の丸を背負い、自分はきっかけでいいのだとして、自分のために祈ったり願ったりするのではなく、誰かの願いや祈りを背負って生きていこうと決意する。自分のためではなく、人のために生き、歌い、音楽をやっていこうと覚悟を決める。もっと伝えたい、もっとわかってほしいと願い、以前より少しだけ聴き手を信じて、言葉を、音を紡ぎだすようになったのだ。
横山は、自分は誰にでもできるような音楽をやっているだけで、特別な人間ではないのだと言う。しかし、だからこその言葉は多くの人たちの共感を呼ぶ。あいつがやれるなら俺たちだってやれる。そう思わせてくれる横山は、やはり「特別な男」なのである。
by 小野島 大
- No.030 山崎洋一郎
- No.029 宇野維正
- No.028 有泉智子
- No.027 柳憲一郎
- No.026 岩崎一敬
- No.025 神庭亮介
- No.024 阿刀大志
- No.023 増田勇一
- No.022 西廣智一
- No.021 平林道子
- No.020 大貫憲章
- No.019 ジョー横溝
- No.018 椎名宗之
- No.017 兵庫慎司
- No.016 尾藤雅哉
- No.015 高橋美穂
- No.014 山口智男
- No.013 DAWA
- No.012 坂野晴彦
- No.011 徳山弘基
- No.010 櫻井 学
- No.009 吉田幸司
- No.008 遠藤妙子
- No.007 中沢純
- No.006 鹿野 淳
- No.005 上野拓朗
- No.004 有島博志
- No.003 小川智宏
- No.002 小野島大
- No.001 石井恵梨子
![横山健 -疾風勁草編- ドキュメンタリーフィルム / これは、横山健が何を背負い、何を信じてきたかを知る物語。[無邪気に手にいれてしまったモノ。持て余すほどの期待と希望。それらに翻弄されながらも、いつでも自分が立つべき場所に立とうとした横山健。これは、横山健が何を背負い、何を信じてきたかを知る物語。]](https://shippukeiso.pizzaofdeath.com/wp-content/themes/shippu-pc2/images/main.jpg)