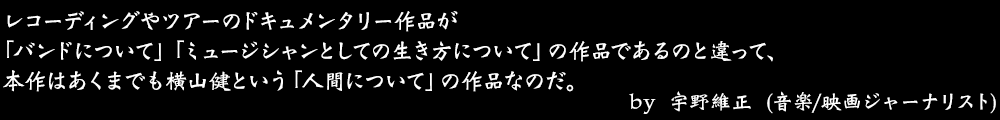作品レビュー:No.029 宇野維正 (音楽/映画ジャーナリスト)
例外は数限りなくあるが敢えて原則を言うと、映画とは監督のものである。一方でミュージシャン/バンドの音楽ドキュメンタリー作品、これは本質的にミュージシャン/バンドのものである。それはマーティン・スコセッシ(ザ・バンドやボブ・ディランやローリング・ストーンズ)が撮ろうが、ジョナサン・デミ(トーキング・ヘッズやニール・ヤング)が撮ろうが、ジム・ジャームッシュ(ニール・ヤング)が撮ろうが同じことで、そのようなビッグネームでさえそうなのだから、ましてや無名の監督にとっては、自身の映画監督としてのキャリアにはあまり大きな影響をもたらさない。多くの場合、そこにあるのは監督の対象への純粋な愛や執着である(時には、純粋なビジネスであることもあるが)。そして、観客の足を劇場へと運ばせるのも、対象への愛や執着である。
もっとも、近年はそうした音楽ドキュメンタリー作品の既存の構造からこぼれ落ちるような作品に光が当たる機会も増えてきた。80年代メタルバンドの不遇の日々と束の間の栄光を描いた『アンヴィル! 夢を諦めきれない男たち』や、歴史に忘れ去られていた一人のミュージシャンの異国での奇跡の復活劇を描いた『シュガーマン 奇跡に愛された男』はその筆頭だろう。これらの作品の重要なポイントは、主役であるミュージシャン/バンドがほとんど知られていないので、そのバイオグラフィー自体が観客にとってまずは大きなツカミになること。こういう作品は口コミで広がっていくことが多い。
本作『横山健 疾風勁草編』は、そのどちらでもない。作品の成り立ち的には前者の比重の方が高いが、曲が丸ごと流れるのはほぼエンドロールのみという作りからも明白なように、大好きなミュージシャンの演奏する姿を大きなスクリーンで体験してスカっと気持ちよくなる、というような作品では全然ない。また、日本のパンクを代表する人気ミュージシャンであり、滅多に取材を受けないミステリアスなミュージシャンでもない(むしろ近年は饒舌と言ってもいいだろう)横山健が語る言葉の一つひとつは、熱心なファンにとってはほとんどが既知のものだろう。したがって、「横山健のことを知らなければ知らないほど作品のインパクトが増す」けれど、「横山健のことを知らない人はこの作品を観ようとしないだろう」という、大きな矛盾がそこに生まれてしまう。
強いて類作を挙げろと言われれば、『メタリカ:真実の瞬間』(最近公開された3Dのやつじゃない方ね)、『ピクシーズ/ラウド・クァイエット・ラウド』、eastern youthの『極東最前線 / 巡業~ドッコイ生キテル街ノ中~』、bloodthirsty butchersの『kocorono』あたりの作品がパッと思い浮かぶが、どれもちょっと違うんだよなぁ。それらのレコーディングやツアーのドキュメンタリー作品が「バンドについて」「ミュージシャンとしての生き方について」の作品であるのと違って、本作はあくまでも横山健という「人間について」の作品なのだ。
というわけで、ここからはそんな「人間について」の作品に対する、極めて個人的な感想。この文章を読む人の中には気づかれている方もいるかもしれないが、音楽ジャーナリストとしての自分は、横山健と常に距離のある場所で仕事をしてきた。AIR JAM 2000は現場にいたし、フェスやイベントなどでは何度も彼のステージを見ているけれど、インタビューをしたこともなければ、ディスクレビューも多分一回も書いたことがないんじゃないかな。しかし、この作品を観て個人としての自分は、横山健と(物理的に)かなり近い距離にいたことを初めて知った。生まれた年も1年しか違わず、東京での生まれた町も環八を挟んですぐ近く。もしかしたら、子供の頃にどこかの公園で一緒に遊んだことがあるかもしれない(多分、一つ年上のクソガキ横山健は相当おっかない存在だったはず)。プロになってからのキャリアの長さもほぼ同じだし、息子がいるのも同じ。作中で彼が吐露している、子供時代における父親と自分との距離の遠さと現在の自分と息子との距離の近さのギャップに戸惑うというのも、すごく身に覚えのある感覚だ。そんなことを考えながら本作を観ていたら、「どうして差がついたのか……。慢心、環境の違い」というあのネット上の有名な定型文がふと頭をよぎってしまった(笑)。
by 宇野維正 (音楽/映画ジャーナリスト)
- No.030 山崎洋一郎
- No.029 宇野維正
- No.028 有泉智子
- No.027 柳憲一郎
- No.026 岩崎一敬
- No.025 神庭亮介
- No.024 阿刀大志
- No.023 増田勇一
- No.022 西廣智一
- No.021 平林道子
- No.020 大貫憲章
- No.019 ジョー横溝
- No.018 椎名宗之
- No.017 兵庫慎司
- No.016 尾藤雅哉
- No.015 高橋美穂
- No.014 山口智男
- No.013 DAWA
- No.012 坂野晴彦
- No.011 徳山弘基
- No.010 櫻井 学
- No.009 吉田幸司
- No.008 遠藤妙子
- No.007 中沢純
- No.006 鹿野 淳
- No.005 上野拓朗
- No.004 有島博志
- No.003 小川智宏
- No.002 小野島大
- No.001 石井恵梨子
![横山健 -疾風勁草編- ドキュメンタリーフィルム / これは、横山健が何を背負い、何を信じてきたかを知る物語。[無邪気に手にいれてしまったモノ。持て余すほどの期待と希望。それらに翻弄されながらも、いつでも自分が立つべき場所に立とうとした横山健。これは、横山健が何を背負い、何を信じてきたかを知る物語。]](https://shippukeiso.pizzaofdeath.com/wp-content/themes/shippu-pc2/images/main.jpg)